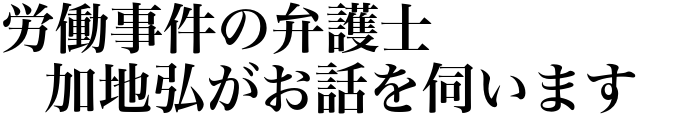解雇のとき、円満退職でないときの退職金トラブル
【前のページ】 « 経営が苦しいから払いたくない
退職金の支払いを巡って労働者と会社がトラブルになりやすい第2のケースは、労働者の退職が円満なものではなかったケースです。
しかし退職金の支払いが制度化されている場合、つまり労働者への支払いが義務となっている場合、 原則として、会社は後から理由をつけて勝手に支払いを拒むことができません。 支給額を減らすことについても同様です。
支払いを拒みたい(減額したい)場合があるのなら、予めそういうルールを決めておく必要があります。 懲戒解雇された従業員には支給をしない、といった内容のものです。 このルールのことを「不支給条項」、「減額条項」といいます。
いいえ、それさえ原則としては許されません。 横領で受けた被害を弁償してもらうつもりなら、退職金を一旦支払ったうえで、改めて損害賠償を求めるのが筋とされます。
しかし労働者との合意があれば相殺も許されるので、横領した労働者に退職金が全額支払われるケースは、実際にはそう多くないだろうと思われます。
不支給条項・減額条項は何でも認められるわけではない
退職金制度があるにも関わらず、会社が退職金の不支給や減額を行おうというのであれば、予め不支給条項や減額条項を定めておく必要があることを見てきました。
しかし、不支給・減額条項がありさえすれば、会社は自由自在にいくらでも退職金の不支給や減額を行うことができるのかといえば、 全くそんなことはありません。
それどころかたとえ不支給・減額条項があっても、裁判所が実際に退職金の不支給や減額を認めるのは、かなり限られたケースだけです。 労働者の悪質性が相当に高いケースでない限り、不支給などまず認められません。
会社の定めた不支給条項や減額条項は決して万能ではなく、裁判になればその内容の妥当性が裁判所に厳しくチェックされるということです。
経営者はおそらくこの点を奇妙に思うはずです。↓
だって退職金って、もともと会社にとって出す義務のないものでしょ?
いったん退職金規程を定めたらそのルールに会社が縛られるのはまぁわかるにしても、 どんなルールで支払うかは会社が自由に決めていいはずじゃないの? なんで裁判所にとやかくいわれないといけないのさ。
それは退職金が「賃金の後払い的な性質」を持っているからです。 会社が退職金制度を用意するとき、経営者はきっと次のようなことを考えるはずです。↓
また従業員も次のように考えているかもしれません。↓
つまり退職金制度が存在する会社においては、退職金は賃金(毎月の給料)と完全に分離されているわけではなく、 むしろ毎月の給料の一部が積み重なって退職金になっている・・・とまではいえないにせよ、それに近い現実があるはずです。
会社は従業員の毎月の給料から一定の額を天引きし、それを退職金の原資にしている・・・とまではいえないにせよ、それに近いことをしているわけですから、 そのお金をどのようなルールで支払うかについて、会社が完全に自由に決めることは許されないのです。
退職金のそうした特殊な性質を指して、「退職金は賃金の後払い的な性格を持つ」という表現がよく用いられます。
規程が存在する場合に従業員が会社に退職金を請求できる根拠は、 単に「会社が支払うことを約束したのだから払いなさい」ではないのです。 「賃金のようなものだから払いなさい」というところに根拠があります。 後者の方が請求の根拠が強いのです。
いいえ、そこまでいうことはできません。 もしそこまでいえるのであれば、借りたものは返すのが当然ですので、会社はいかなる理由でも退職金を減額したり払わなかったりすることができない理屈となります。
それでは世の実情に合わないということで、「退職金は賃金の後払いである」ではなく、「賃金の後払い的な性格を持つ」と、 やや奥歯に物の挟まった表現を用いることで、裁判所は不支給・減額を条件付きで認める余地を残しているのです。
なおここでいう「退職金」は、「制度化されている場合の退職金」のことです。 制度化されていない(支払う決まりがない)場合では、賃金の後払い的性格は無く、恩恵的な給付であると見なされます。
だからこそそうしたケースでは、支払うか支払わないか、支払うとすればいくら支払うか、を原則として会社が自由に決めていい理屈となるのです。
話を戻しましょう。 会社が退職金の不支給や減額を行おうというのであれば、予め不支給条項や減額条項を定めておく必要があるのですが、 一方でそうした条項があれば無条件に有効となるわけでもなく、その内容の妥当性が裁判所に厳しくチェックされる、という話でした。
例えば次のような不支給条項は、妥当であるとは見なされないでしょう。↓
- 円満退職でないときは不支給とする
- その他、会社が不適当と見なしたときは不支給とする
一方で次のような不支給条項であれば、基本的に妥当であるといえるでしょう。↓
- 懲戒解雇された従業員には不支給とする
- 退職後に懲戒解雇事由が発覚した従業員には不支給とする
そういう規定を設けている会社が多いでしょうし、 懲戒解雇されて仕方がないといえる程の事情が労働者にあったのであれば、裁判でも不支給が認められる可能性が高いといえます。
懲戒解雇された従業員にも過去に会社が退職金を支払ったことがある、など労働者側に有利な材料があれば、 全額の不支給までは認められず、一部支払いが命じられることも中にはあります。しかし例外的なケースです。
むしろ懲戒解雇そのものの有効性を争う方が、勝算が高いでしょう。
懲戒解雇は簡単にできるものではないからです。
懲戒解雇を巡っては、次のような問題も起こり得ます。↓
懲戒解雇されて仕方のないことをしたんですが、会社との話し合いで何とか自己都合退職にしてもらいました。
そのかわり退職金は出さないからと言われ、仕方ないかとその場は納得したんですけど、 よく考えてみるとうちの会社の規程には、「懲戒解雇された労働者には退職金を支給しない」と書いてあるだけなんです。
僕は結果的に懲戒解雇されなかったわけですから、この規程によれば退職金を請求する権利があるんじゃないのかなーと。 そんな虫のいい話はやっぱりないですかね?
経営者はこう思うでしょう。↓
ところが問題にします。 実際に懲戒解雇されていない労働者に、「懲戒解雇の場合は支払わない」という内容の不支給条項を適用することは、原則として認められません。
いかにも融通が利かなすぎると経営者には映るかもしれませんが、 先述の通り、退職金には「賃金の後払い的性格」があり、さらには退職後の生活保障という面もあるので、 会社が支払いを拒否するための根拠は相当に厳しく判断されるのです。
今回のケースでは、会社は「懲戒解雇に相当する事由がある場合には退職金を支給しない」と予め定めておけば、不支給が認められる可能性が高かったのですが、 実際にそうした規定を置いていない会社も少なくなく、しばしば争いになります。
すると経営者はこう考えるものです。↓
じゃあ今からしてあげるわ、覚悟なさい!
しかしこれも認められません。
原則として、退職が成立した労働者を後から懲戒することはできないからです。
懲戒解雇されたくない一心で、自分から飛びついたんでしょ!
もしも裁判になれば、その辺りが争いになるでしょう。 会社と労働者の間でどのような話し合いが行われたのか、また労働者の懲戒事由の悪質性なども問題となります。
労働者の立場でいえば、そもそも本当に懲戒解雇されて仕方のないケースであったのかも疑ってみるべきです。 懲戒解雇は簡単にできるものではないからです。
【前のページ】 « 経営が苦しいから払いたくない